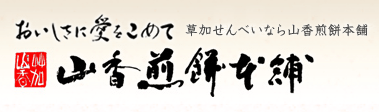ちまきに込められた心
 端午の節句の祝い菓子といえば関東では「柏餅」が一般的ですが、関西では圧倒的に「ちまき」が多くなります。ちまきは上新粉ともち粉とを合わせてつくった生地を熊笹の葉で包み、い草でぐるぐると巻いて蒸したものです。
端午の節句の祝い菓子といえば関東では「柏餅」が一般的ですが、関西では圧倒的に「ちまき」が多くなります。ちまきは上新粉ともち粉とを合わせてつくった生地を熊笹の葉で包み、い草でぐるぐると巻いて蒸したものです。
日本の食文化は中国から伝えられたものが多いのですが、端午の節句に欠かせないこの「ちまき」も例にもれず中国の故事に由来していました。
起源前、中国の楚国に屈原(くつげん:BC340~278)という政治家がいました。当時の王の信頼を得て若くして政治家としての手腕を発揮していましたが、その活躍ぶりからまわりの者に妬まれ足を引っぱられて官を辞して詩人となりました。その後の国の行く末を嘆き、62歳の時、泊羅(べきら)の淵に身を投げました。人々はていねいに彼を弔い、命日の5月5日には竹の筒に米を入れて川に投じ、霊に捧げました。が、それを川に住む竜が盗んでしまうので、米を「おうち」(せんだん)の葉で包み、5色の糸で縛って捧げるようになりました。これがちまきの始まりといわれています。おうちの葉は香りがあって竜がきらうといわれており、また5色の糸は「木火土金水」の五行を表わし、邪気を払うと信じられていました。
今も旧暦5月5日の屈原の命日には、中国の人々はその供養をし、ちまきを食べる習慣が残っているそうです。日本に伝わったのは平安時代。宮中での端午の儀式に使われるようになり、以後、関西を中心に全国に広まったといわれています。ちまきには二千年もの間、屈原の愛国心を賛え、その死を悼む中国の人々の心が込められていたのです。